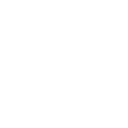【初心者ドライバー必読】自動車保険の選び方!

はじめて車を購入された方
学生で車をレンタルして旅行に行く方
車があれば行動範囲が広くなり、気分が高まりますよね。
一方で、車の運転には事故のリスクがつきまといます。
そんな時に必要になってくるのが自動車保険です。
自動車保険は、もし事故にあった時に私たちを守ってくれる保険です。
「車をはじめて買うけど、保険に加入したほうがいいの?」
「レンタカーを借りるだけだから、保険はつけなくていいでしょ?」
「運転はうまいほうだから、事故しない自信がある!」
車にはじめて乗る方やあまり乗ったことのない方は、このように考える人も多いのではないでしょうか。
この記事では運転初心者、車をレンタルする方などに向けて、保険に加入することの重要性と保険の選び方について解説していきます。
自動車保険の役割とは?
保険に加入したことがない人は、自動車保険と聞くと、「事故したときに何か補償してくれるもの」というくらいの認識だと思います。
しかし、自動車保険は大きな役割を担っています。
ここでは、その役割について解説していきます。
自動車保険には2種類の保険がある
自動車保険には、強制保険の「自動車損害賠償責任保険」(以下自賠責保険)と、自賠責保険を補う「任意保険」があります。
自賠責保険は被害者救済のための最低限の保険
自賠責保険は事故にともない、相手を死傷させてしまった損害を補償するものです。
これを「対人賠償」といいます。
相手の車に損害を与えてしまった場合や、自分がケガをしてしまった場合に補償を受けることはできません。
補償される金額に対して、限度額がもうけられています。
傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は4,000万円、死亡による損害は3,000万円です。
任意保険はさまざまなリスクに対応する保険
任意保険は対人賠償に加え、対物賠償、人身傷害保険、車両保険など、自動車運行に関するさまざまな損害に対応した保険です。
はじめて新車を購入したけど運転に自信がない方であれば、車両保険の補償を手厚くするなど、補償内容をカスタマイズできるのが特徴です。
補償内容が厚いほど、保険料は高くなります。
未加入の場合のリスク
自賠責保険と任意保険の違いについて理解していただけたと思います。
もし自賠責保険だけで、任意保険に加入していなかった場合、事故を起こしてしまったらどうなるのか例を使って説明していきます。
事故例1(車×人の死亡事故)
車を運転中、右折時に横断歩道を歩いていた人をひいて死亡させてしまった。
損害賠償額は3億3,000万円だったケース。
この場合、任意保険に加入していなければ、自賠責保険で補償できるのは3,000万円のみです。
残りの3億円は自分で負担しなければなりません。
事故例2(車×電車)
電車の接近に気づかず、遮断機、警報機のない踏切に進入した。あわてて踏切を通過しようとしたところ、脱輪してしまった。電車はそのまま車に衝突し、線路脇に立つ家屋に飛び込んで停車した。
損害賠償額は、電車への損害、復旧工事費、家屋への損害で、約1億2,000万円ケース。
この場合、任意保険に加入していなければ、自賠責保険で補償できるものは何もないので、全額自己負担ということになります。
このように任意保険に加入していなければ、事故を起こした際に多額の損害賠償を負担する可能性があります。事故のリスクの大きさを考えると、任意保険に加入することをオススメします。
どんな補償内容にすればよいの?
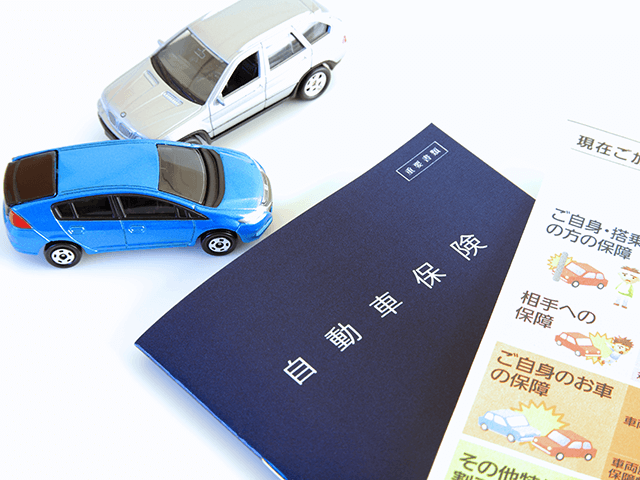
ここまでの説明で、任意保険に入ろうと思う方も増えたと思います。
その一方で、どんな補償内容にすればいいのかと疑問に思う方も増えたと思います。
ここで任意保険で重要となる補償内容について解説していきます。
必ずつけるべき補償
以下の補償内容は必ずつけておくべきものです。
・対人賠償責任保険・対物賠償責任保険
対人・対物賠償責任保険は、保険金額を無制限に設定しておくことが必要です。
上記の事故例のとおり、対人・対物事故のどちらの場合においても、損害賠償額が数億円に及ぶリスクがあるからです。
そのようなリスクに備えて、対人・対物賠償責任保険は無制限にしておくと安心です。
・人身傷害保険または搭乗者傷害保険
人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、車に搭乗中の事故で自分自身または、搭乗者がケガや死亡してしまった場合に補償される保険です。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、ケガを補償するという意味では同じですが、保険金の支払われ方に違いがあります。
人身傷害保険は「実損」補償といわれるタイプの保険です。
保険金額を限度にかかった費用分だけ補償されます。
一方、搭乗者傷害保険は「定額」補償といわれるタイプの保険です。
入院や通院の日数によって保険金が支払われる「日数払い」や、ケガの症状や部位によってあらかじめ定められた金額が補償される「部位症状別払い」があります。
ケガの症状が確定次第、保険金が支払われるので、人身傷害保険に比べて保険金の支払いはスピーディです。
必要最低限の補償だけでよいのであれば、人身傷害保険だけに加入し、上乗せとしての補償が必要であれば、搭乗者傷害保険に加入することをオススメします。
安心のロードサービス
任意保険には基本的に無料のロードサービスがついています。
ロードサービスを利用しても、翌年の等級は下がりませんので、もしもの時も安心です。
ロードサービスには以下のようなものがあります。
- レッカーサービス 突然の故障など緊急時に車をけん引してくれるサービス。
- バッテリー切れ 路上でのバッテリー上がりを直してくれるサービス。
- キーとじ込み 鍵の紛失や車内に置いたまま外に出た時の対処をしてくれるサービス。 保険会社によってロードサービスの内容が異なるので、保険選びの一つの基準にしてみるのもよいと思います。
保険料の相場
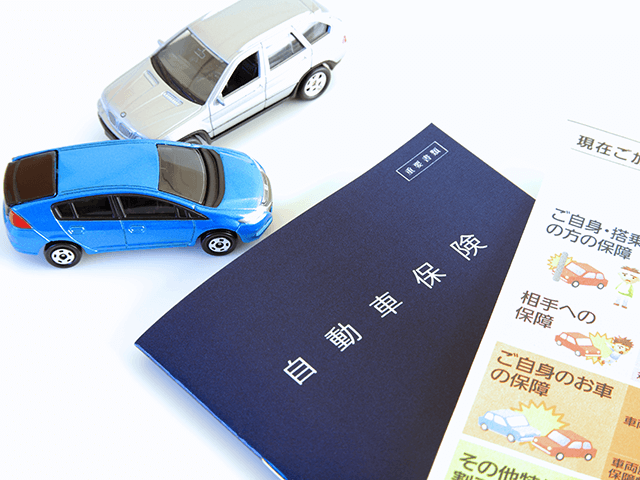
入るべき補償内容は分かったけど、「保険料が高いんじゃないの?」と思っている人もいると思います。
ここでは自動車保険の保険料はどのくらいになるのか、また保険料を安くする方法について解説していきます。
保険料は人によって異なる
多くの保険会社が「リスク細分型」の自動車保険を販売しています。
事故を起こすリスクが低い人は、保険料が安くなります。
どのような要素で保険料が安くなるのか解説していきます。
- 免許証の色 5年間無事故、無違反だった場合に与えられる「ゴールド免許」を持っていた場合、保険料の割引を受けられます。
- 年間走行距離、使用目的 使用目的が日常・レジャーで、年間走行距離が少ないほど、保険料は安くなります。 業務用の場合、運転時間、走行距離ともに長くなり、事故を起こすリスクが高くなるため、保険料が高くなる傾向にあります。
- 年齢 記名被保険者の年齢によって保険料は異なります。 10~20代は免許を取りたてのため、70代は認知機能の低下のため、事故を起こすリスクが高くなり、保険料が高くなります。それ以外の年代では事故を起こすリスクが低くなるため、保険料は割安となります。
- 等級 自動車保険には等級というものがあります。 1等級から20等級があり、等級が上がるほど保険料は安くなります。 保険期間1年の間に保険を使わなければ、1等級ずつ上がります。 保険加入時、基本的に6等級から始まるので、どうしても保険料は高くなります。
- 車種 「型式別料率クラス」という、自動車の車種ごとに決められた率が保険料に反映されます。 たとえば、高級車ほど事故したときの修理費が高くなるので、保険料は高くなります。
保険料を安く抑えるには?
初心者の方は等級が低いので、どうしても保険料が高くなってしまいます。
少しでも保険料を安くするために保険料の割引制度を活用しましょう。
- インターネット割引 いわゆる「ダイレクト型」の自動車保険で適用されている割引です。 インターネットで契約手続することで、保険料が割引かれます。
- 新車割引 車の初年度登録年月から25か月以内に保険開始日がある場合に、保険料が割引されます。適用条件は各社で異なりますので、保険会社に確認するようにしてください。
新車を新しく購入して、保険に加入しようとしている初心者にはぴったりの割引制度だといえますね。
まとめ
ここで、これまでの内容をまとめてみようと思います。
- 自動車保険には、「自賠責保険」とそれを補う「任意保険」の2種類ある。
- 任意保険に未加入で事故を起こした場合、多額の費用を自己負担しなければならない可能性がある。
- 対人・対物賠償は無制限で、人身傷害又は搭乗者傷害保険は自分に適した保険金額で加入されることをオススメします。ロードサービスは無料でついているので、もしもの時も安心です。
- 保険料は、あまり自動車に乗らない方は保険料を抑えることができます。さらに、インターネット割引や新車割引などを活用することで、さらにお得に自動車保険に加入することができます。
どうですか皆さん、この記事を読んで自動車保険の選び方について理解できましたか?
初心者だからこそ任意保険に加入して安心・安全のカーライフを送りましょう。
| この記事を書いた人 | |
|---|---|
 | ニッセンライフ |
| Will Naviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセンのグループ企業です。 40年以上の豊富な経験と実績をもつ保険代理店です。 ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが、保険でお悩みの点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。 | |