民間介護保険の仕組みと選ぶときの3つのポイントを徹底解説
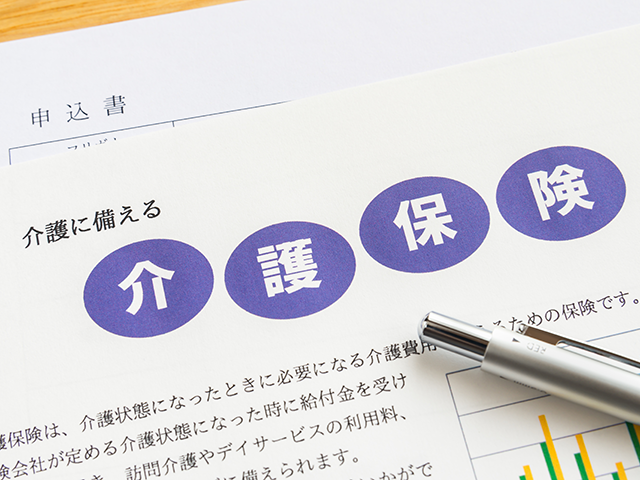
内閣府「令和3年版高齢社会白書」によると、2020年の日本の総人口のうち、65歳以上人口割合(高齢化率)は28.8%となっています。
2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になるといわれており、今後も超高齢社会が進んでいくでしょう。
高齢者の生活を支える公的介護保険は、改正によって自己負担が増えており、自分で介護費用を準備する必要が高くなっています。
そこで活用したいのが「民間介護保険」なのです。
本コラムでは民間介護保険の仕組みを解説し、どんな保障・お金を準備できるのかはもちろん、選ぶときのポイントをご紹介します。
このコラムを読めば自分に必要な介護保障のヒントが得られるはずです。
公的介護保険の「現物給付」に対して民間介護保険は「現金給付」
民間介護保険は、保険会社が販売している保険商品です。
所定の要介護状態などに該当した場合に保険金を「一時金」や「年金」などで受け取れます。
対して公的介護保険は、要介護認定を受けた利用者が1~3割の利用料を支払い、介護サービスが受けられる「現物給付」が原則となっています。
比較表:公的介護保険と民間介護保険の違い
| 公的介護保険 | 民間介護保険 | |
|---|---|---|
| 給付 | 介護サービスが受けられる 現物給付(一部、現金による給付あり)。 | 一時金や年金などで受け取れる現金給付 |
| 給付金額 | 要介護度に応じて決定 | 契約時に自分で設定した金額 |
| 給付対象者 | 第1号被保険者(65歳以上)は要介護(要支援)度に応じて 第2号被保険者(40歳以上、65歳未満)は特定疾病の方のみ | 被保険者 |
| 保険料の支払い | 40歳になった月から一生涯 | 65歳など一定年齢までのタイプや、一生涯タイプなどが選べる |
| 保険料払込免除 | なし | 保険会社所定の条件に該当すれば適用 ※保険商品によって異なる |
| 税制優遇 | 社会保険料控除(全額) | 生命保険料控除 |
年金から介護サービス費用を支払い続けることが負担になる可能性があり、民間介護保険には「公的介護保険で補えない部分に備える」役割を持っています。
なお、平均年金月額は厚生年金保険の場合13~15万円、国民年金で5~7万円。
居住地域や世帯人数などによって変わるものの、少し心もとない金額だと感じられるのではないでしょうか。
民間介護保険なら1~3割のサービス利用料(自己負担額)に備えられることはもちろん、介護のために家をリフォームする・有料老人ホームの入居一時金などの大きなお金に備えられます。
このように、公的介護保険と民間介護保険には給付条件などが異なるため、それぞれの特性を理解した上で準備する必要があります。
民間介護保険はなに保険?保険の基本的な仕組み
この章では、民間介護保険を検討するときに知っていてほしい保険の仕組みについて解説します。
介護保障が主契約なのか特約なのかをチェックしましょう
保険は一般的に「主契約」と「特約」(オプションにあたるもの)からできています。
保険商品を見るときは、介護保障が主契約なのか特約なのかを確認しておきましょう。
| 区分 | 主契約 | 特約 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 介護保障 | その他 |
| 介護保障付死亡保険 | 死亡保障 | 介護保障 |
| 介護特約付医療保険 | 医療保障 | 介護保障 |
たとえば、すでに医療保険に加入している場合に介護特約付医療保険に加入すると、医療保障部分が重複します。
保障が手厚くなる分保険料の負担も大きくなるので注意が必要です。
民間介護保険の給付要件と保険金の受取方法
保険はいざというときに保険金が支払われなければ加入している意味がありません。
保険金請求をしなければ保険金は受け取れないので、保険金が支払われる条件・受取方法をしっかり理解しましょう。
商品によって違いがでやすいところでもあるので、比較・検討するときには確認することが大切です。
【給付要件】
給付要件は大きく分けて公的介護保険連動型と独自型の2つがあります。
・公的介護保険連動型
要介護1以上など、要介護度にあわせて保険金の支払い条件を設定しています。もし改正などで変更があった場合、民間介護保険の保障内容も変わる可能性があります。
・独自型
保険会社所定の介護状態に該当した場合に保険金が支払われます。
たとえば、寝たきりの状態が一定期間継続している・認知症と診断確定されたなどです。
独自基準は保険会社の商品によって異なるため、比較・検討が難しい傾向があります。
契約後に「思っていた保障と違う」といったことがないように、どんな状態になると保障を受け取れるのか、よく確認しましょう。
【受取方法】
保険金の受け取り方法には、「一時金」、「年金」、「一時金・年金併用」があります。
介護費用を備えるといっても、必要になるお金はさまざま。
保険でどれくらい備えておきたいのか、保険料の支払いと貯蓄のバランスも考慮して選ぶようにしましょう。
・一時金タイプ
特徴:保険金を1回でまとめて受け取れる
メリット:家のリフォーム代や介護ベッドの購入など、まとまったお金が必要になる介護初期費用にあてられる
デメリット:介護が長引いた場合に、金額が不足する可能性がある
・年金タイプ
特徴:1年に1回など契約時に設定した期間で継続して保険金が受け取れる
メリット:介護サービスの自己負担金額など、継続的にかかる介護費用に備えられる
デメリット:一時金タイプよりも保険料が高くなる傾向がある
・一時金・年金併用タイプ
特徴:一時金と年金の両方受け取れる
メリット:初期費用にも継続してかかる費用にも備えられる
デメリット:保険料が高い
民間介護保険を選ぶときの3つのポイント

実際に民間介護保険を選ぶとなると、何を基準に選べばいいのか難しいと思います。
そこで、最低限チェックしてほしい3つのポイントをまとめました。
比較・検討するときにパンフレットなどで確認してみてください。
1. 貯蓄型と掛け捨て型 それぞれの特徴
貯蓄型の多くは、介護保障以外にも死亡保障や年金保障があり、解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)があるタイプです。
貯蓄性がある分保険料は割高になっています。
掛け捨てが嫌な人、介護保障はもちろん遺族の生活費や老後の生活費としても備えたい人にオススメです。
掛け捨て型は、解約返戻金や満期保険金などを抑えた・なくしたタイプの保険。
保険料が割安で、介護保障のみなどシンプルな保障内容になっていることも多いです。
介護保障を上乗せしたい人や、貯蓄は別でして保障だけを備えたいという人に向いています。
2. 保障される期間と保険料を支払う期間の違い
保険の専門用語で保障される期間を「保険期間」、保険料を支払う期間を「保険料払込期間」といいます。
保険料をみて単純に高い・安いで判断するのではなく、保険期間と保険料払込期間の条件が同じかどうかも確認しましょう。
| 定期型 | 終身型 | |
|---|---|---|
| 保険期間 | 10年や〇歳までなど 一定期間 | 一生涯 |
| 保険料払込期間 | 保険期間と同じことが多い | 10年や〇歳までの短期払 ずっと払い続ける終身払 |
| 保険料 | 割安 | 割高 |
| 更新 | あり | なし |
| 向いている人 | 割安な保険料で備えたい 保障内容を見直す可能性がある | 一生涯の保障がほしい 途中で保険料が上がらない方がいい |
3. 公的介護保険が考慮されているか・保障が重複していないか
公的介護保険だけでは足りない部分を補うのが民間介護保険の役割です。
- 実際に自分が介護を受けることになったときの給付はどうなるのか
- 年金はいくらくらいもらえるのか
- 介護費用としていくらくらい準備できそうなのか
などを考慮して保険を選ぶことで、保障の過不足を防ぎ保険料の無駄がなくなります。
また、実際に商品を選ぶときに注意しておきたいのが、すでに加入している保険の保障内容です。
[民間介護保険はなに保険?保険の基本的な仕組み]で説明したように、介護保障だけではなく死亡保障や医療保障がセットになっている場合は、保障が重複していないか確認しましょう。
保険商品によっては途中で保障を追加できる「中途付加」というものがあり、今加入している保険に介護保障を付けられる可能性があります。
加入している保険会社や代理店に問い合わせて確認することをオススメします。
民間介護保険は複数の商品を比較して自分にピッタリの商品を選びましょう
介護に備えるといってもどのように介護を受けたいのかは人それぞれ。
受けたい介護サービスによって必要になるお金も変わります。
希望する介護を受けるためにあるのが公的介護保険や民間介護保険です。
民間介護保険を選ぶときは、複数の商品を比較・検討することが大切です。
しかし、保障内容や保険金の受け取り方など自分で考えて選ぶことは難しいと思います。
ニッセンライフではお客さまのご意向などをおうかがいし、保険商品をご案内する「無料保険相談サービス」を提供しています。
また、お金の専門家・FPに老後の生活資金を含めた貯蓄方法などお金について幅広く相談できるサービスもあります。
保険だけではなく貯蓄もしっかりしておきたいという方にはこちらのサービスがオススメです。
| この記事を監修した人 | |
|---|---|

| 伊藤 可菜 |
大手生命保険会社の勤務を経て、2020年にニッセンライフに入社。 | |
出典
「令和3年版高齢社会白書」(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/gaiyou/03pdf_indexg.html
掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。
出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。


willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。