持病があっても入りやすい死亡保険とは?失敗しない選び方と目的ごとのおすすめ商品を紹介!

持病のある方にとってハードルが高いと思われた生命保険。
今では告知項目が少ない引受基準緩和型保険や、健康状態の告知が不要の無選択型保険があり保険に入りやすくなりましたが、病気治療中や過去に入院や手術の経験があっても通常の死亡保険に入れる可能性があることをご存知でしょうか?
このコラムでは通常の死亡保険と持病がある方向けの死亡保険の違いや、保険の選び方について解説します。
持病がある方向けの死亡保険とは
過去に治療歴や現在治療中の病気があると保険に加入することが難しい理由の一つとして、健康状態の告知を求められる点にあります。
保険に加入する際は、健康状態など保険会社から求められた事項を正確に告知する義務があります。
通常の死亡保険の場合は、過去5年・・・投薬の有無など詳しい告知が求められます。
一方、持病がある方向けの保険は、告知項目が簡単・シンプルな内容で、あてはまる項目がなければ申込できます。
持病があっても入れる保険には、引受基準緩和型と無選択型の2種類があり、それぞれの特長とおすすめ商品を紹介します。
引受基準緩和型死亡保険 おすすめ商品3選
引受基準緩和型保険は2~4つ※の簡単な告知項目にあてはまらなければ申込みできる保険で、その分保険料が割増されています。
※告知項目は保険会社・保障内容 によって異なります。
「終身保険ライズ・サポート・プラス」 オリックス生命保険株式会社
おすすめポイント
- 死亡保障が一生涯続き、保険料は加入時のまま上がらない。
- 200万円(50歳~85歳は100万円)から、100万円単位で保険金額を選べる。
- 掛け捨てではなく、解約払戻金がある。
月払保険料例(保険金額:200万円コース・終身の場合)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
40歳 | 5,934円 | 4,910円 |
50歳 | 7,452円 | 5,860円 |
60歳 | 10,148円 | 7,524円 |
【試算条件】保険金額200万円コース 保険期間・保険料払込期間:終身 保険料支払方法:月払(口座振替扱)の場合 2026年1月1日現在
※保険会社のWEBサイトに移動します。
「かんたん告知はなさく定期」 はなさく生命保険株式会社
おすすめポイント
- 最長90歳まで保障する定期保険。
- 保険金額は200万円から設定できます!90歳満期かつ、契約年齢60歳以上の場合は100万円、契約年齢70歳以上の場合は50万円から設定可能※最低保険金額は、契約年齢や保険期間によって異なります。
- 解約払戻金をなくして保険料を抑えました!
月払保険料例(保険金額:200万円・90歳満期の場合)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
40歳 | 3,326円 | 2,582円 |
50歳 | 5,602円 | 3,950円 |
60歳 | 8,448円 | 5,440円 |
【試算条件】死亡保険金額:200万円 保険期間・保険料払込期間:90歳 保険料支払方法:月払の場合 2026年1月1日現在
※保険会社のWEBサイトに移動します。
「SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険」 SBIいきいき少額短期保険株式会社
おすすめポイント
- 満20歳から84歳の方まで申込み可能。毎年更新することで100歳*まで保障を継続できる。*被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、100歳の誕生日前日までが保障期間です。
- 保険期間は1年なので、生活に合わせて見直しやすい。
- 手ごろな保険料でお葬式代程度の備えができる。
月払保険料例(保険金額:200万円・1年更新の場合)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
40~44歳 | 2,540円 | 1,740円 |
50~54歳 | 3,760円 | 2,200円 |
60~64歳 | 5,860円 | 3,020円 |
【試算条件】死亡保険金額:200万円 保険期間・保険料払込期間:1年 保険料支払方法:月払の場合 2025年10月1日現在
※保険会社のWEBサイトに移動します。
無選択型死亡保険 おすすめ商品2選
無選択型保険は、申込み時に健康告知や医師の診査が不要なので、直近で入院や手術があった方も入りやすい商品です。
ただし、責任開始時前に発病していた病気で亡くなった場合は払込保険料相当額が死亡保険金額として支払われるケースがあることや、一定期間持病は保障対象外になる可能性があること、引受基準緩和型よりもさらに保険料が割高になっています。
「終身保険どなたでも」 アフラック
おすすめポイント
- 満40歳から満80歳までの方なら健康状態にかかわらず申込可能。
- 月々の保険料は2,000円から1,000円単位で契約できる。※契約年齢・性別によって、契約いただける最低保険料が異なります。
- 契約時の年齢、保険料の払込年数に応じて解約払戻金があり、保障は一生涯。
受取保険金額例(月払保険料6,000円コース・終身の場合)
契約年齢 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) | 死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) | |
40歳 | 1,672,200円 | 6,688,800円 | 2,058,000円 | 8,232,000円 |
50歳 | 1,257,000円 | 5,028,000円 | 1,609,800円 | 6,439,200円 |
60歳 | 906,600円 | 3,626,400円 | 1,183,200円 | 4,732,800円 |
【試算条件】6,000円コース 個別取扱 保険期間・保険料払込期間:終身 保険料支払方法:月払の場合 2025年10月1日現在
※この保険は無選択型であり、通常のアフラックの終身保険よりも保険料が割増されています。
ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。
「無告知型葬儀保険「みんなのキズナ」」 あんしん少額短期保険株式会社

おすすめポイント
- 40歳から79歳の方まで申込み可能。1年ごとに99歳まで更新できる。
- 保険金額は10万円を単位として最高100万円まで設定できる。
- 保険金直接支払サービス特約を付加することで、葬儀の事前相談が無料、全国の提携葬儀社で葬儀が可能で、葬儀代は直接保険金から支払える。
月払保険料例(保険金額:100万円・1年更新・初年度の場合)
契約年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
40歳 | ※月払申込不可。 | ※月払申込不可。 |
50歳 | 1,160円 | ※月払申込不可。 |
60歳 | 2,160円 | 1,380円 |
※保険会社のWEBサイトに移動します。
持病があっても通常の死亡保険に入れる可能性がある
実は、病気治療中や過去に入院や手術の経験がある方でも通常の死亡保険に入れる場合があります。
無条件で加入できる可能性もありますが、以下のような条件付きで加入できるケースもあります。
- 通常よりも高い保険料を支払う(保険料の割増)
- 持病を含む特定の病気が保障の範囲から外れる(特定部位(疾病)不担保)
- 契約から一定期間は保険金の額が削減される(保険金の削減)
持病がある方向けの死亡保険は、加入しやすくなっている分、基本的に通常の保険よりも保険料が高くなります。
保険料は、通常の保険→引受基準緩和型保険→無選択型保険の順に高くなるため、まずは通常の死亡保険で加入できないか調べてから検討するようにしましょう。
持病があっても通常の死亡保険が検討できるかどうかの目安
- 病気の種類
子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣嚢腫・白内障・緑内障・高血圧・高脂血症(脂質異常症)・大腸ポリープは治療中であっても通常の死亡保険にご加入いただけた事例があります。
- 治療状況
診断されてから何年経過しているか(治療期間)、現在の治療状況(投薬治療、経過観察など)、入院・手術の経験の有無など
- 併発している病気の有無
複数の病気で治療歴があっても、それぞれが通常の死亡保険が検討できる条件であれば入れる可能性があります。
※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。健康状態だけではなく、職業などその他の告知や申込内容で総合的に審査判断されます。
保険会社によって引受目安などが異なるため、A社では申込みが難しい場合でも、B社なら申込みできたというケースがあります。
個々に調べるのは大変なので、複数の保険会社の取り扱いがある代理店など保険のプロに相談して保険を探すことをおすすめします。
なお、持病を隠したり、実際の治療歴とは異なることを告知して保険に加入することは「告知義務違反」にあたり、保険金が支払われないことや契約を解除される可能性があります。
もし、事実の不告知・不実の告知をして保険に加入できたとしても、保険金支払い時に行われる保険会社の調査で間違いなく発覚するので、結局は自分に不利益になるだけです。
事実をありのままに正確に告知できるように、おくすり手帳を管理する、入院や手術をしたときの領収書等の書類をしっかり保管するなど、いつでも治療歴を確認できるようにしておきましょう。
もし治療歴が曖昧な場合は、何となく申告・告知するのではなく、かかりつけ医に確認するなどの対応を行いましょう。
通常の死亡保険と引受基準緩和型死亡保険、無選択型死亡保険の違い
| メリット | デメリット |
|---|---|---|
通常の死亡保険 | 保険料が安い 商品や特約の選択肢が多い | 持病・既往症があると加入が難しい |
引受基準緩和型死亡保険 | 無選択型死亡保険よりも保険料が安い 告知項目が少ないため、持病があっても入りやすい 持病・既往症を含めて保障される | 通常の死亡保険よりも保険料が高い 通常の死亡保険よりも商品や保障の選択肢が少ない 契約から一定期間保険金額が減るなどの条件が付くことがある |
無選択型死亡保険 | 告知をする必要がないため、健康状態にかかわらず加入できる | 引受基準緩和型死亡保険よりもさらに保険料が高い 商品や保障内容の選択肢が少ない 契約から一定期間保険金額が減るなどの条件が付くことがある |
持病がある方向けの死亡保険の選び方
持病がある方向けの商品であっても、通常の死亡保険の選び方と基本的には同じです。
しかし、持病がある方向けの死亡保険はは、保険金額が一定期間削減されるなど条件ついている商品があるので、場合によっては将来見直しをする可能性を考慮して商品を選定しましょう。
死亡保険の目的に合わせて保険期間(保障する期間)を選ぼう
死亡保険には、一生涯保障が続く終身保険と、10年間や90歳までなどの一定期間のみを保障する定期保険があります。
持病がある方向けの保険にも両方のタイプがあるので、死亡保険を備えたい目的にあわせてどちらが必要なのかを見極める必要があります。
例えば、葬儀代や身辺整理資金に備えたい場合は終身保険が適しており、子供が独立するまで、定年退職するまでなどで一時的に大きな保障が必要な場合は定期保険が適しています。
終身保険は一般的に掛け捨てではなく解約返戻金があるタイプが多いので、定期保険と比べると保険料が高くなる傾向があります。
また、保険は契約時の年齢によって保険料が決まるため、同じ保障内容であっても高齢になるほど保険料が高くなります。
終身保険で葬式代を備えたいけど予算に合わないという場合は、定期保険で備えることも手段の一つです。
厚生労働省によると、男性の平均寿命は81.09歳、女性は87.13歳となっているため、90歳満了や100歳まで更新できるタイプの定期保険であれば、予算内で検討できる可能性もあるでしょう。
ただし、定期保険の場合、保険期間よりも長生きした場合に保障切れになるリスクがあるので注意が必要です。
複数の商品から保障内容の比較をしましょう
同じ持病がある方向けの死亡保険であっても保障内容・支払条件が異なるケースがあるため、必ず複数の保険を比較するようにしましょう。
例えば、引受基準緩和型死亡保険では、加入から1年以内に病気で亡くなった場合、保険金額の半分しか保障されない場合があります(不慮の事故や感染症での死亡を除く)。
また、無選択型保険では、契約日から一定期間内に疾病で死亡した場合は、保険金ではなく払い込んだ保険料相当額の受取となることもあります。
保険は加入したら終わりではない!持病がある方向けの死亡保険に加入する場合は、定期的に見直しをしましょう
持病があっても保険に加入できれば、ほっと一安心できると思いますが、保険は見直しも大切です。
加入した当時は持病がある方向けの死亡保険しか検討できなかったとしても、保険商品自体が改定になり申し込めるようになっていることがあります。
特に、無選択型死亡保険に加入している方の場合、入院や手術から1~2年以上経過しているなど治療状況が変わっていると、引受基準緩和型死亡保険の告知項目に該当しなくなり、検討できるようになっていることがあります。
無選択型死亡保険から引受基準緩和型死亡保険に代わるだけでも、保険料が安くなったり、希望する保障内容に変えられる可能性もあります。
見直しのたびに保障内容や告知項目などの情報収集するのは時間も手間もかかるので、保険代理店などの複数の保険会社の取り扱いがある保険代理店に相談することをおすすめします。
まとめ
持病がある方が死亡保険を検討するときは、まず通常の死亡保険で検討できないか調べることから始めましょう。
引受基準緩和型死亡保険・無選択型死亡保険に加入できた場合でも、健康状態が良くなっていたり、商品改定などによっては通常の死亡保険が検討できるようになる可能性もあるので、定期的に見直しをすることも大切です。
保険の比較をしたり見直しをするための情報収集には時間と労力がかかるので、プロの手を借りるのが一番効率的です。
ニッセンライフではお客さまの健康状態やニーズをお伺いしたうえで、複数の保険会社の中からぴったりの商品を紹介いたします。
特に持病がある方向けの保険は、創業当初から得意としている分野であるため、長年のノウハウを生かしたご提案が可能です。
お客さまのご要望に合わせて、3つの相談方法をご用意しております。
- 対面・訪問相談:直接会って相談したい、幅広いプランから選びたい方におすすめ
- WEB面談:外出が難しい、対面で相談したいけど抵抗がある方におすすめ
- 電話相談:スキマ時間に気軽に相談したい方におすすめ
どの相談方法を選んでも相談料は無料、何度でも相談ができます。
保険のことで悩んだときはぜひニッセンライフにご相談ください。
※こちらは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は通常の定期保険・終身保険と比べて割増しされています。
※健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない定期保険・終身保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
※ご契約の内容等によっては、累計払込保険料が保険金額を上回る場合があります。
※募集代理店株式会社ニッセンライフ、及び、その関連会社、グループ会社の役員・社員は、法令により募集代理店株式会社ニッセンライフを通じて当ページ掲載商品の申込みはできません。
| この記事を監修した人 | |
|---|---|

| 條 武尊 |
保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、大学課程(TLC)、証券外務員 | |
出典
厚生労働省「令和6(2024)年簡易生命表」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/index.html
掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。
出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。



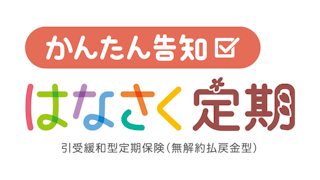




willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。