自律神経失調症でも入れる・加入できる保険

病気解説
自律神経失調症とは

自律神経失調症は、言葉の通り、「自律神経が失調した状態」=「自律神経がうまく働かない状態」と考えられます。例えば、暑くもないのに汗をかいたり、ほてったり、逆に暖かい季節に急に手足が冷たくなったりする場合や、緊張しているつもりはないのに口が渇き、動悸、息切れ、締め付けられるような頭痛、心窩部痛(みぞおちの痛みのこと)、腹痛、下痢と便秘を繰り返す場合などです。
では、自律神経はどのような働きをしているのでしょうか。
自律神経は、自分の意志では動かすことができない神経であり、自分の意志とは無関係に、自動的に外部の刺激や情報に反応して、身体の機能をコントロールしています。また、呼吸や体温調節など、生命を維持するために必要な根源的な機能をつかさどっていることから、自律神経は、植物系神経とも呼ばれています。
交感神経と副交感神経
自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があり、それぞれ全く反対、真逆の作用を持っています。
交感神経は、いわば「緊張の神経」です。例えば運動会で短距離走のスタートラインに立ったところを想像してみてください。スタート前の緊張で、体温は上がり、目や口は乾き、汗をかき、鼓動は早く、呼吸は浅く早くなり、スタートダッシュに備えて筋肉が緊張します。また、緊張状態では、唾液をはじめとした消化液の分泌が減少し、食べ物を運ぶための胃腸の動き が低下するため、食べても消化されず、腹部の張り や便秘、下痢といった変化もあらわれます。
これに対し、副交感神経は、いわば「リラックスの神経」です。リラックスして眠りにつく場面を想像してください。体温は下がり、目や口は潤い、汗は引き、鼓動はゆっくり、呼吸も深くゆっくりになり、全身の筋肉が弛緩します。また、リラックス状態では、消化液の分泌も増加し、胃腸の動 きが活発になるため、おなかが空き、便の状態 も整います。
このように、自律神経は、体の内外の刺激や環境の変化に自動的に反応し、交感神経と副交感神経を働かせたり休ませたりしながら、私たちの体のバランスを自動調整しています。「自動で体のバランスを律する神経」、それが自律神経です。
自律神経がうまく働かず、暑くもないのに汗をかくなど本来とは異なる反応をすると、「自律神経が乱れた」とされますが、なぜこのような状態が引き起こされるのでしょうか。
自律神経失調症の原因
自分の意志と関係なく、自動的に生命活動を維持している自律神経(交感神経と副交感神経)の働きは、我々の脳によってコントロールされています。
知覚や理性、判断など高度な精神活動をつかさどる「大脳皮質」、食欲、睡眠欲、性欲など本能的欲求や、怒りや快感などの情動など生命活動をつかさどる「大脳辺縁系」、自律神経と内分泌のコントロールセンターとして生命活動をつかさどる「視床下部」、これらが相互的に機能的に作用し、自律神経のバランスを整えています3)。
しかし、大脳皮質の理性が強すぎて、大脳辺縁系の欲求や情動が抑えつけられると、大脳皮質と大脳辺縁系の間にひずみが生じ、大脳辺縁系と視床下部の間の伝達もスムーズにいかなくなり、視床下部は自律神経をうまくコントロールできなくなるといわれます。結果、お互いにバランスを取り合うはずの交感神経と副交感神経のリズムが乱れ、自律神経失調状態につながります。
また、驚きや恐怖などの不快な刺激が長時間または頻回に続いたり、精神的なストレスが大きすぎたりする場合も、交感神経が常に興奮したままの状態となり、次第に視床下部のコントロール機能が低下します。その結果、自律神経のバランスが崩れ、身体の内外からの刺激や情報に対して適切に反応することができなくなります。視床下部は男性ホルモンや女性ホルモン の分泌にも深くかかわっているため、視床下部の機能が低下すると、女性では月経異常などが生じます。
さらに、不規則な生活も自律神経のリズムを崩す原因だといわれています。私たちの体は、昼間の活動時間帯は交感神経が優位となり、夜の休息時間帯は副交感神経が優位となります。したがって、夜更かしや朝寝坊を繰り返すと、視床下部のコントロール機能が損なわれ、自律神経のリズムが狂います。その結果、休んでいるはずなのに交感神経が興奮して、動悸、発汗、のぼせ、筋緊張亢進、食欲低下、不眠などの症状があらわれ、活動したいのに、交感神経が働かず、動けない、力が入らない、集中できない、眠いなどの症状が出てきます。
ストレス社会といわれる現代においては、規則正しい生活が送れず、十分な睡眠がとれない場合も多々ありますが、睡眠不足や昼夜逆転といった交感神経優位のライフスタイルは、自律神経失調のみならずストレス関連性疾患のリスクとなりますので改善が必要です。
自律神経失調症の原因
自律神経は末梢神経のひとつで、全身にあるため 、自律神経失調症では以下のような多彩な症状がみられます 。
| 分類 | 症状 |
|---|---|
| 全身症状 | 微熱、全身倦怠感 |
| 頭 | 頭痛、頭重感、片頭痛、緊張型頭痛、ふらつき、抜け毛 |
| 目 | 眼精疲労、かすみ目、目の乾燥 |
| 耳 | 耳閉塞感、耳鳴り、めまい |
| 鼻 | 嗅覚異常、鼻腔乾燥 |
| 口 | 口渇、唾液減少、味覚異常 |
| 喉 | 咽喉頭異常感(喉のつまり、異物感、圧迫感など) |
| 呼吸器 | 呼吸困難感、息切れ、過呼吸 |
| 循環器 | 動悸、不整脈、血圧変動、立ちくらみ |
| 消化器 | 心窩部痛、腹痛、嘔気、腹部膨満感、下痢、便秘、腹鳴、食欲低下 |
| 泌尿器 | 頻尿、残尿感 |
| 生殖器 | 機能不全、月経異常 |
| 四肢 | ほてり、冷感、しびれ、感覚異常、手汗、足汗 |
| 皮膚 | 乾燥、多汗、蕁麻疹、皮膚掻痒感、肌荒れ |
| 筋肉・関節 | 肩こり、背中こり、腰痛、関節痛 |
| 精神症状 | 不眠、不安・焦燥感、抑うつ感、悲哀感、集中力低下、記憶力低下、無気力など |
自律神経失調症の診断・検査
私たちがよく耳にする 「自律神経失調症」ですが、実はいまだに学会が推奨する明確な診断基準や定義はなく、正式な病名ではないのです。そのため、上記のような様々な自律神経症状を訴えるにもかかわらず、検査上、明らかな異常が見つからない場合に、自律神経失調症と診断されることが多いものの、自律神経失調症を診断する有用な検査はありません。一方、各種器質的病変(臓器や組織そのものに異常が生じて症状が現れる病変)や精神疾患でも同様の自律神経失調の症状がみられる ことがあるため、ほかの病気が原因になっていないか確認が必要です 。必要に応じて、以下の検査が実施されます。
| 検査項目 | 除外される病気 |
|---|---|
| 頭部CT/MRI | 頭部の病気 |
| 血液検査、尿検査 | 貧血や糖尿病、甲状腺機能異常など |
| 胸部レントゲン/CT | 悪性腫瘍、肺炎、肺気腫など |
| 心電図 | 心臓の病気や不整脈など |
| 内視鏡検査、腹部レントゲン/CT、超音波検査 | 悪性腫瘍、逆流性食道炎、消化管の潰瘍、炎症性の腸の病気など |
うつ病や、パニック症、社交不安症などの不安症、身体症状症 (身体的な異常がないにも関わらず、痛みや胃腸症状、しびれなどの身体症状が長く続く病気)などの精神疾患でも、前述のような様々な自律神経失調症状が出現することがあります。身体的精査の結果、何も異常が見つからない場合は、精神疾患の身体症状や機能性内科疾患の可能性を考慮して、精神科や心療内科を受診することをおすすめします。症状に応じて、各種心理テストが実施されることもあります。
保険加入
自律神経失調症でも入りやすい保険とは
自律神経失調症で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に入れる可能性があります。
自律神経失調症で治療中の方が保険を選ぶときのポイントをみてみましょう。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
自律神経失調症で治療中の方が入りやすい引受基準緩和型保険とは
引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方が入りやすくなっています。
もし自律神経失調症が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。
ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。
1.最近3か月以内に、医師の診察・検査または健康診断・がん検診・人間ドックを受けて、入院または手術、がんの疑いでの再検査・精密検査をすすめられたことがある(ただし、再検査・精密検査の結果、がんまたはその疑いが否定された場合は含みません)
2.過去1年以内に、病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことがある
3.過去5年以内に、下記の病気と新たに診断されたこと(再発や転移を含む)、あるいは下記の病気により入院したこと、または手術を受けたことがある(がん・肝硬変・統合失調症・アルコール依存症・認知症)
全ての告知項目が「いいえ」であればお申込みいただけます。
※上記は保険会社の健康状態の告知項目例です。告知項目は保険会社・保障(補償)内容によって異なります。また、お仕事の内容や他の保険契約の加入状況などにより、ご加入いただけない場合があります。
自律神経失調症は完治している場合や治療状況などによっては、通常の保険に加入できる可能性もあります。
詳しくはニッセンライフのコールセンターまでお問合せください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

引受基準緩和型保険では加入が難しいという場合は無選択型保険
直近で入院や手術の経験があるなど、告知に該当して加入が難しいという場合は、無選択型保険を検討してみましょう。
無選択型保険は医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。
ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始時以前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。
ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。
保険の選び方で迷ったときはニッセンライフにご相談ください
引受基準緩和型保険の告知項目は商品によって項目数や告知内容が異なるため、A社の商品では加入が難しくてもB社なら加入できたというケースがあります。
また、以前と比べて引受基準緩和型保険でも通常の保険と同じような保障内容が選べることや、自由にカスタマイズできる商品もあるので、既契約の有無やライフスタイルに合わせて複数商品から比較・検討することをおすすめします。
ニッセンライフでは複数の保険会社の取り扱いがあり、お客さまのご希望に合わせて商品のご紹介・ご説明・申し込みのお手伝いを行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法
自律神経失調症の治療法
治療方針は患者の症状や生活によって異なりますが、心と体の両面からアプローチする全人的医療が基本となります。そのため、内科や外科で一通り検査をしたものの異常が見つからなかった場合は、体と心の両面からアプローチすることができる、「内科・心療内科」を受診することをおすすめします。信頼できる医師を見つけ、その医師と一緒に、心と体のつながりを理解しながら治療を受けましょう。
また、生活習慣の見直しと改善も重要です。十分な睡眠がとれているか、バランス良く適量な食事がとれているか、運動不足ではないかなどの評価がおこなわれます。ウォーキングをはじめとしたエクササイズは、ストレス改善効果が見込めますので、積極的に生活に取り入れてください。
体に働きかける治療としては、抗うつ薬、抗不安薬、漢方薬などによる薬物療法があります。 体調の状況により処方されるため、体調が改善したからといって自分の判断で服用回数を減らしたり、中断することはせず、主治医に相談しましょう。
心に働きかける治療としては、支持的精神療法、解決志向型アプローチ、交流分析、認知行動療法などの心理療法があります。必要に応じて、その人に合った心理療法が選択されますので、主治医とよく相談しながら進めることが重要です。
腹式呼吸、漸進的筋弛緩法、自律訓練法などのリラクゼーションも効果的です。症状に対する対処行動(ストレスに対してそれを軽減したり克服したりするために行う行動で、コーピングともいう)としてだけでなく、症状の予防にも非常に効果があります 。
自律神経が全く乱れなくなることは考えづらく、季節の変わり目にはだれでも自律神経が乱れやすくなります。大切なことは、自律神経の変化に気づき、それに対処できるようになることです。
心身相関への気づきとセルフコントロールが、治療の最終ゴールとなりますので、自ら積極的に自律神経の変化に向き合い、体と心の 回復を目指していきましょう。
医療情報の監修

坂本 典之
よこはま本町通りクリニック院長
略歴
東京大学大学院卒業 医学博士
都立墨東病院、藤枝市立総合病院、東京大学医学部附属病院、いずみ記念病院にて、総合内科・心療内科医として研鑽を積んだのち2023年よりよこはま本町通りクリニック開設
所属学会・専門医
日本内科学会: 総合内科専門医、
日本心療内科学会 日本心身医学会: 心療内科専門医、
日本医師会認定産業医
所属学会
日本内科学会
日本心身医学会
日本心療内科学会
日本サイコオンコロジー学会
日本不安症学会
日本アレルギー学会
目次
よくある質問
「自律神経失調症と保険」に関する相談例
持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、自律神経失調症の方から多くのご相談があります。
主な質問とその回答例をご紹介します。
自律神経失調症と診断され、定期的に通院をして経過観察をしています。投薬治療をしていないので通常の保険に入れますか?
回答はこちら
経過観察での通院も治療の一種なので、通常の保険に入るのは難しいです
ただし、治療状況など引き受け基準は保険会社や商品によって異なるため、詳しく状況をお伺いできれば、検討しやすい保険を提案できる可能性があります。
詳しくはニッセンライフまでお問合せください。
自律神経失調症の治療に専念するため仕事を辞めました。悪化したりほかの病気になったときに備えて保険に入りたいのですが入れますか?
回答はこちら
告知項目に該当しなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります
保険に加入するときには職業や年収について告知する必要がありますが、保険会社や商品によっては休職中や無職の場合でも申し込みできる商品はあります。
自律神経失調症以外の病気で治療中ですが保険に入れますか?
回答はこちら
病名や治療歴によっては保険に入れる可能性があります
自律神経失調症以外の病気についても、引受基準緩和型保険の告知項目に該当しなければ、引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。
相談をする
ニッセンライフでは、自律神経失調症の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。
電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み
対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み


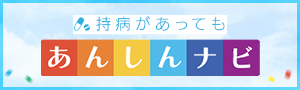
willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。