肝硬変でも入れる・加入できる保険

病気解説
肝硬変とは

B型・C型肝炎などのウイルス感染や、アルコール、脂肪肝、自己免疫性疾患など、さまざまな原因により肝臓に炎症が起こることがあります。この炎症が慢性的に進行すると、炎症を修復する過程で線維化(線維状のタンパク質が広がった状態)が起こり、これが肝臓全体に広がります。線維化が広がり、肝臓が硬くなった状態が肝硬変です。肝硬変が進行すると徐々に肝機能が低下します。肝機能がまだ保たれており症状のない肝硬変を「代償性肝硬変」、肝機能が低下して様々な症状や合併症があらわれている肝硬変を「非代償性肝硬変」といいます。肝臓は再生力がある臓器ですが、肝硬変になってしまうと再生しにくくなります。そのため肝硬変が進行するとさまざまな症状が出現します。
肝硬変による症状
肝硬変になることでさまざまな変化があらわれます。たとえば、肝硬変により肝臓が線維化し固くなると、肝臓の中を血液が流れにくくなります。そうなると、肝臓に流れる血管のひとつであり、腸から吸収された栄養分を運ぶ門脈が肝臓の中を通りにくくなるため、肝臓を通らず直接胃や食道の静脈へショートカットする側副血行路(そくふくけっこうろ・短絡路)を作ります。この短絡路によって胃や食道に静脈瘤が形成されます。静脈瘤の血管が大きくはれてくると血管が弱くなり、破裂すると大出血を起こして吐血したり、下血しショック状態となったりすることがあります。
また、肝臓は、門脈を通ってきた栄養豊富な血液に含まれるアンモニアなどの有毒物質を毒性の低い物質に変換し、尿に排泄する解毒の役割を担っています。肝硬変により門脈の血液が肝臓を通らずに短絡路を経由して全身へめぐると、毒性物質が脳内に蓄積して神経機能障害を引き起こします。これが肝性脳症です。肝性脳症は、意識がもうろうとしたり、鳥が羽ばたくように手が震えるような症状がみられたりすることがあります。(改行挿入)加えて、門脈が肝臓に流れ込みにくくなることで門脈内の圧力が上がり、血液中の血しょうが腹腔内へしみだし、腹水も溜まりやすくなります。肝臓でのタンパク質(アルブミン)の生成量が減少するため血液中のタンパク質の濃度が低下し、血管外に水分が漏れ出ることも腹水がみられる原因のひとつです。
その他には、胆汁の排泄ができなくなることで黄疸がみられ、体や白目が黄色くなります。腹水や胆汁の排泄障害などが影響し、食欲が低下します。(改行挿入)出血傾向がみられることも肝硬変の代表的な症状のひとつです。門脈の圧力が高くなり、流れる血流が増えて腫れた脾臓は、止血の働きをする血小板を破壊して減少させます。また、肝硬変になると肝臓で産出される血液凝固因子が減少し、出血しやすくなります。これらの原因が重なり、鼻出血などの出血が起こりやすくなります。
肝硬変の原因
肝硬変の原因には以下のような病気が挙げられます。
- ウイルス性(B型肝炎、C型肝炎)
- 自己免疫性(自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎)
- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)※※2024年8月より代謝異常関連脂肪性肝疾患(MASH)へ名称が変更となりました。
- アルコール性
- 代謝性(ヘモクロマトーシス、ウイルソン病)
以前はウイルス性肝炎からの肝硬変の割合が多くなっていましたが、治療の進歩により現在はウイルス性肝炎による肝硬変の頻度は減少傾向です。2008年の肝硬変の原因調査ではC型肝炎が60.9%、アルコール性13.6%、NASH2.1%と圧倒的にウイルス性が多い結果でした。しかし、2023年の結果ではアルコール性35.4%と最も多くなり、C型肝炎23.4%、NASH14.6%と初めてアルコール性がウイルス性肝疾患を抑え最多の原因となっています。
肝硬変の検査
肝硬変の病状を把握するためには、血液検査と画像による検査がよくおこなわれます。それぞれについて解説します。
血液検査
血液検査では以下の項目について調べられます。
| 項目名 | 概要 |
|---|---|
| アルブミン | 肝臓で作られるタンパク質です。肝硬変になると低下します。 |
| コリンエステラーゼ | 肝臓で作られるタンパク質です。アルブミンと同様に肝硬変で減少します。 |
| 総ビリルビン | 黄疸の程度を表す値です。肝硬変では上昇します。 |
| アンモニア | 肝臓での解毒作用が低下すると血液中で増加し、肝性脳症の原因となります。 |
| 血小板 | 止血をするために働く血球です。肝硬変では減少し、出血しやすくなります。 |
| プロトロンビン時間 | 血液が固まる時間を表します。肝硬変になると血液凝固因子が減少してプロトロンビン時間が正常時と比べて長くなります。 |
| M2BPGi* | 肝臓の線維化の進行度がわかります。また、B型肝炎、C型肝炎、NASH症例では病期の進行に伴い上昇します。 |
| FIB-4 index | 肝臓での線維化を予測する数値です。肝硬変が進行すると上昇します。 |
この他にも、肝硬変の原因が特定できていない場合には、原因を特定するための血液検査がおこなわれます。例えば、B型、C型の肝炎の感染が無いかを調べたり、自己免疫性肝炎が疑われる場合には抗核抗体、抗平滑筋抗体、抗LKM抗体、原発性胆汁性胆管炎が疑われる場合には抗ミトコンドリア抗体などの自己抗体を測定する場合もあります。
画像検査
- 腹部超音波検査
超音波検査では肝硬変が進行すると、肝臓の表面が凸凹し、肝臓の内部が粗く見えるようになります。 - 肝硬度測定(フィブロスキャン)
超音波を利用し、特殊なプローブ(超音波を発し、内部の情報を得るための装置)から弱い振動を発生させ肝臓内をつたわる速度を測定します。この検査により肝臓の硬さを算出し、肝線維化の進行を評価することができます。 - MR elastography(MRE)
MRIを利用して肝臓の硬さを測定し、線維化を評価します。 - CT検査
CTでは肝臓の表面の凹凸の程度や腹水、また肝臓がんの合併がないかを調べることができます。造影剤を使用することで血管の走行が確認でき、短絡路の存在を確認・評価します。
保険加入
肝硬変でも入りやすい保険とは
肝硬変で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に入れる可能性があります。
肝硬変で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをみてみましょう。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
肝硬変で治療中・治療歴がある方が入りやすい引受基準緩和型保険とは
引受基準緩和型保険は、通常型の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。
引受基準緩和型保険は、持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。
ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。
告知項目は保険会社や商品によって異なります。
肝硬変の場合は5年以内に診断、入院、手術を受けたことがあるかどうかが重要になりますが、保険を引き受けるかどうかの判断基準は保険会社や商品により異なるため、A社の商品では加入が難しくてもB社なら加入できたというケースがあります。
ニッセンライフでは複数の保険会社の取り扱いがあり、お客さまのご希望に合わせて商品のご紹介・ご説明・申し込みのお手伝いを行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

引受基準緩和型保険では加入が難しいという場合は無選択型保険
無選択型保険は医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。
ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始日以前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。
ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。
ニッセンライフではお客さまが備えたい保障はもちろん、すでに加入している保険があるかどうかや、公的保障なども加味したうえで、検討しやすい保険をご提案いたします。
保険選びで迷ったときは、ニッセンライフにお問合せください。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法
肝硬変の治療法
肝硬変そのものに対する治療はあまりありません。しかし、肝硬変となった原因により、一部の病気では、原因の病気を治療することで肝硬変が改善することがわかってきました。
●原因となる病気の治療
B型、C型肝炎に対しては、抗ウイルス薬を使用することで肝機能の改善がみられることがわかってきました。抗ウイルス薬を使用することが可能かどうかも含め、主治医と相談をしてみましょう。また、自己免疫性肝炎ではステロイドなどを使用することにより元の病気をコントロールすることが重要です。アルコール性肝炎では禁酒することが大切といえます。
●適切な栄養を摂取
肝硬変になると低栄養になりやすくなります。そのため、十分なエネルギーを摂り、バランスの良い食事をすることがとても大切です。
特にアルブミン値が3.5g/dL以下の場合、適切な食事量と充分なタンパク質の摂取、減塩も必要となります。肝硬変になると肝臓でエネルギーを作り出すことができず、飢餓状態に陥りやすいため、エネルギー不足を補う目的で食事の回数を1日4〜5回に分割したり、就寝前に補食をおこなう栄養療法がすすめられています。しかし、この栄養療法は、食べ過ぎることでかえって肥満になり、病状が悪化することもあるので注意が必要です。必ず主治医に確認をしながら食事の摂取方法を検討しましょう。
また、肝硬変となり肝臓の機能が低下すると、アンモニアやアミノ酸の代謝がうまく行われなくなり、人体にとって有害なアンモニアが血中で増加します。その結果筋肉が肝臓に代わってアンモニアを解毒する役割を担いますが、その際、分岐鎖アミノ酸(BCAA)が使用されるため、BCAAの不足が起こります。運動時のエネルギー源であり、同時に筋肉中のタンパク質を合成する材料でもあるBCAAが不足すると、筋力が低下してしまう恐れがあります。BCAAを補充する薬物療法は、栄養状態を改善し、アンモニアの代謝を促す効果があります。
●合併症に対する治療
肝硬変ではさまざまな合併症が起こります。そのため、合併症に対する治療も必要です。例えば、腹水が溜まりやすくなるため、利尿剤の投与やアルブミン製剤を点滴投与します。場合によりおなかに針を刺して腹水を抜く治療をおこなうこともあります。
また、肝硬変によりできた食道や胃の静脈瘤は大出血につながることもあり、命を落とす原因にもなります。このため、内視鏡で予防的結紮術や硬化療法をおこない、事前に出血を防ぐ処置をします。
肝性脳症に対しては、合成二糖類を投与することでアンモニアの産生・吸収の抑制ができます。
●肝移植
腹水や黄疸が一般的な治療によっても改善しない場合、基準を満たせば肝移植も検討されます。
肝移植には、生体肝移植と脳死肝移植があります。以前と比較すると脳死肝移植の件数は増えましたが、日本ではドナー(提供者)が不足しているため、肝移植を希望しても必ず受けられるわけではありません。基準を満たした場合には検討するべきですが、生体肝移植には倫理的な問題もあります。よく主治医と相談をして決めていきましょう。
治療費
肝硬変の治療費
肝硬変にはさまざまな治療法がありますが、ここではウイルス性肝炎に対する抗ウイルス剤と肝移植のおおよその治療費について解説します。
●抗ウイルス剤使用時の治療費
B型、C型の肝炎に対して抗ウイルス剤治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)をすることで、線維化の改善や肝細胞がんの発生を抑える効果があると報告されています。これらの治療は医療費が高額になりますが、医療費の助成制度(肝炎治療特別促進事業)を利用できるため、自己負担額は患者の世帯所得により月額1万円または2万円となります。
●肝移植での治療費
基準を満たす肝移植の場合には、医療保険が適用されます。一般的に肝移植の入院は約1~2か月程度となります。また、費用は3割負担の場合、食事療養費や全身麻酔管理費用、入院にかかる費用などを合計して約500万円程度です。そのほかにも差額ベッド代やおむつ代などの雑費が別にかかります。
負担軽減に関しては、高額療養費制度やその他の医療費助成制度もあるため、病院や行政の窓口で相談をしてみましょう。ただし、入院中の食費(食事療養費)や差額ベッド代は対象外です。
なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。
病気データ
肝硬変のデータ
肝硬変は慢性肝炎の結果起こる病態です。日本肝臓学会の肝がん白書(令和4年度)によると、日本では、約30万人以上の肝硬変患者が存在すると推計されています。肝硬変の原因となる疾患は、B型肝炎、C型肝炎などのウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、非アルコール性脂肪性肝疾患(NASH)など多岐にわたります。
日本での肝硬変の2023年の全国調査において、肝硬変の原因疾患の割合はアルコール性が35.4%、C型肝炎が23.4%、NASHが14.6%と報告されています。2018年の調査まではC型肝炎が継続してトップを走っていましたが、近年の抗ウイルス剤による治療の進歩により、ウイルス性肝炎を原因とする肝硬変の割合は激減しました。一方、アルコールやNASHなどの生活習慣に伴う肝硬変の割合は増加傾向であり、注意が必要です。
健康診断などでAST、ALTなどの肝トランスアミナーゼ、γGTPの上昇を指摘されたら、早めに原因を調べましょう。もし、生活習慣に伴う肝障害であれば早めの生活習慣の見直しが大切です。
出典・参考文献
日本消化器病学会「肝硬変診療ガイドライン」
https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/kankohen.html日本消化器病学会「患者さんとご家族のための肝硬変ガイド2023」
https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/disease/pdf/kankouhen_2023.pdf日本肝臓学会「肝がん白書 令和4年度」
https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/liver_cancer.html
医療情報の監修

和田 蔵人
プロフィール
佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。
地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。
目次
よくある質問
「肝硬変と保険」に関する相談例
持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、肝硬変の方から多くのご相談があります。
主な質問とその回答例をご紹介します。
6年前に肝硬変と診断され、投薬治療を続けていますが保険に入れますか?
回答はこちら
引受基準緩和型保険であれば入れる可能性があります。
肝硬変の場合、診断・治療開始してからどれくらいたっているかによって、検討できる商品が変わります。
治療開始から6年経過しているのであれば、複数の商品から比較・検討できます。
肝硬変以外の病気で治療中ですが保険に入れますか?
回答はこちら
病名や治療歴によっては保険に入れる可能性があります。
肝硬変以外の病気についても、引受基準緩和型保険の告知項目に該当しなければ、引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。
お問合せいただければ状況をおうかがいの上最適な商品をご紹介することができるので、ぜひお電話・ご相談ください。
肝硬変になるとがんを発症しやすくなると聞きました。がんにも手厚い保険に入りたいのですが入れますか?
回答はこちら
引受基準緩和型医療保険の特約であれば、備えられる可能性があります。
肝硬変で治療中の場合、がん保険の検討は難しいですが、がんの保障を厚くする特約がある引受基準緩和型医療保険であれば保険に入れる可能性があります。
相談をする
ニッセンライフでは、肝硬変の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。
電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み
対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み


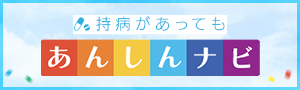
willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。