原発性胆汁性胆管炎でも入れる・加入できる保険

病気解説
原発性胆汁性胆管炎とは

原発性胆汁性胆管炎(Primary Biliary Cholangitis:PBC)は、肝臓で作られる「胆汁(たんじゅう)」という消化液の流れが滞り、その影響で肝臓の機能が徐々に低下していく慢性の肝疾患です。病気の進行はゆっくりですが、時間の経過と共に悪化していくことが特徴です。
この病気では、肝臓内にある細い「胆管」と呼ばれる管が、自己免疫の異常によって傷つけられます。本来、胆管は胆汁を腸まで送り届ける役割を担っていますが、免疫反応によって破壊されてしまうと、胆汁が肝臓内にたまってしまう「胆汁うっ滞」が起こります。
胆汁がスムーズに流れないことで、胆汁中の成分であるビリルビンが血液中に逆流するようになります。さらに病気が進行すると、このビリルビンが体中の組織に蓄積され、白目の部分や皮膚、手のひらなどが黄色くなる「黄疸(おうだん)」と呼ばれる症状が出てきます。
病気の進行と治療の現状
この病気は長い時間をかけて進行します。肝臓に滞った胆汁や炎症によって、肝細胞は徐々にダメージを受けていき、やがて肝臓の組織が固くゴツゴツとした状態になり(線維化)、肝硬変へと進展していきます。肝硬変が起こると、肝臓全体の機能がさらに低下し、黄疸、腹水、意識障害(肝性脳症)といった深刻な症状を引き起こし、最終的には肝不全の状態に至ることもあります。
ただし、すべての患者においてこのように急激に悪化するわけではありません。多くのケースでは病状の進行はかなり緩やかで、日常生活に大きな支障をきたさないまま経過する人も少なくありません。現在では「ウルソデオキシコール酸(ursodeoxycholic acid;UDCA)(ウルソ®)」という薬によって病状をコントロールできることが多く、無症状のまま生活を送る方も増えています。
病名の変遷と発症しやすい人の特徴
この病気は以前、「原発性胆汁性肝硬変」と呼ばれていましたが、実際には、肝硬変に至らず軽度のまま推移する人も多くいます。そのため、「肝硬変」という言葉が誤解を招くことがあるとして、2016年に「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」へと名称が変更されました。
原発性胆汁性胆管炎は特に50〜60代の中高年の女性に多くみられる病気です。最初に現れる症状としては「皮膚のかゆみ」がよく知られており、これが病気に気づくきっかけになることもあります。
原発性胆汁性胆管炎の分類
原発性胆汁性胆管炎は、大きく2つのタイプに分類されます。ひとつは症状がみられるタイプ(症候性)(symptomatic PBC:sPBC)、もうひとつは症状がないタイプ(無症候性)(asymptomatic PBC:aPBC)です。
sPBCでは、胆汁のうっ滞に伴う肝機能障害が原因となり、皮膚のかゆみや黄疸、腹水、肝性脳症、さらには食道や胃の静脈瘤(血管がこぶのように膨らんだ状態)といった症状が出現します。一方、aPBCの場合は検査で異常が見つかったものの、自覚症状がまったくないまま過ぎていくことも珍しくありません。
さらに、sPBCは血液中のビリルビンの値に基づいて次の2つに細分化されます。ビリルビンが2mg/dL以上のものを「s2PBC」、2mg/dL未満のものを「s1PBC」と呼び、病気の進行度合いの目安となっています。
原発性胆汁性胆管炎の経過
原発性胆汁性胆管炎の進行速度や症状のあらわれ方は患者によって異なります。多くの場合、長い年月をかけて少しずつ進行するため、罹患しても適切な管理をおこなうことで通常の寿命を全うできると考えられています。
しかし、中には比較的早い段階で黄疸が出現し、肝機能が急速に悪化してしまうケースも存在します。また、黄疸が見られなくても、門脈圧(腸などから肝臓に流れ込む太い静脈である門脈の血液の圧力)が高まることで食道や胃の静脈瘤が形成される場合もあります。
このような経過の違いから、原発性胆汁性胆管炎は以下の3つのタイプに分類されます。
1. ゆっくりと進行する「緩徐進行型(かんじょしんこうがた)」
2. 初期に黄疸が出現し、肝不全へと進む「黄疸肝不全型(おうだんかんふぜんがた)」
3. 黄疸が現れる前に肝臓の血流に異常が起きているサインがみられる「門脈圧亢進症型(もんみゃくあつこうしんしょうがた)」
これらの分類は、治療方針や今後の回復の見通しを判断する際の参考にされます。
aPBCの(無症候性)の場合には、約70%以上の患者が10年以上病状の進行はありません。一方で、一部の患者においては徐々に皮膚のかゆみや黄疸が生じ、食道静脈瘤や腹水、肝性脳症などの肝障害に基づく症状があらわれます。
原発性胆汁性胆管炎の原因
発症原因については、現在のところ明確には解明されていません。そのため、根治的な治療法はまだ確立されておらず、厚生労働省により指定難病に認定されています。
一方で、自己免疫の異常が関与していることは確実視されており、自分の免疫が誤って胆管を攻撃することで発症する「自己免疫性疾患」のひとつと考えられています。遺伝的な素因や環境要因(感染症や薬剤の関与など)が複雑に関わっている可能性も示唆されています。
原発性胆汁性胆管炎の診断
原発性胆汁性胆管炎の診断には、以下の3つの要素が重要な手がかりとなります。
1. 血液検査で胆汁うっ滞を示す所見(ALPやγ-GTPの上昇)
2. 抗ミトコンドリア抗体(AMA)の陽性(間接蛍光抗体法やELISA法で確認)
3. 肝臓の組織検査で、慢性非化膿性破壊性胆管炎(CNSDC)、肉芽腫、胆管消失などの特徴的な病理所見
これらが揃えば、典型的なPBCと診断されます。肝生検(針で肝臓の細胞を採取し顕微鏡で調べる検査)は、診断が難しいケースや他の疾患との鑑別が必要な際に実施されます。
なお、AMAが陰性でも、臨床所見や肝組織像によってPBCと診断されることがあります。また、肝生検は肝臓の線維化やダメージの程度を評価することにも役立ちます。
原発性胆汁性胆管炎の合併症
原発性胆汁性胆管炎により胆汁の流れが滞ると、さまざまな合併症が引き起こされます。代表的なものには以下が挙げられます。
- 黄疸
ビリルビンの沈着によって皮膚や目が黄色くなる - 皮膚黄色腫
脂質の代謝異常により皮膚に黄色いふくらみができる - 骨粗しょう症・骨折
胆汁の流れが悪くなることでカルシウム吸収が低下し、骨がもろくなる - 門脈圧亢進症
肝臓内の血流が滞ることで、食道静脈瘤や脾臓の腫れが生じる - 肝細胞がん
肝硬変を背景として発生することがある - 肝不全関連の症状
腹水、肝性脳症など - 高コレステロール血症
- シェーグレン症候群
- 関節リウマチ
- 甲状腺疾患(橋本病)
保険加入
原発性胆汁性胆管炎でも入りやすい保険とは
原発性胆汁性胆管炎で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に入れる可能性があります。
原発性胆汁性胆管炎で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをみてみましょう。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
原発性胆汁性胆管炎で治療中・治療歴がある方が入りやすい引受基準緩和型保険とは
引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。
引受基準緩和型保険は、持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。
ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。
1.最近3か月以内に、医師の診察・検査または健康診断・がん検診・人間ドックを受けて、入院または手術、がんの疑いでの再検査・精密検査をすすめられたことがある(ただし、再検査・精密検査の結果、がんまたはその疑いが否定された場合は含みません)
2.過去1年以内に、病気やケガで入院したこと、または手術を受けたことがある
3.過去5年以内に、下記の病気と新たに診断されたこと(再発や転移を含む)、あるいは下記の病気により入院したこと、または手術を受けたことがある(がん・肝硬変・統合失調症・アルコール依存症・認知症)
全ての告知項目が「いいえ」であればお申込みいただけます。
※上記は保険会社の健康状態の告知項目例です。告知項目は保険会社・保障(補償)内容によって異なります。また、お仕事の内容や他の保険契約の加入状況などにより、ご加入いただけない場合があります。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

引受基準緩和型保険では加入が難しいという場合は無選択型保険
無選択型保険は医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。
ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始期前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。
ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。
保険の選び方で迷ったときはニッセンライフにご相談ください
引受基準緩和型保険の告知項目は商品によって項目数や告知内容が異なるため、A社の商品では加入が難しくてもB社なら加入できたというケースがあります。
また、以前と比べて引受基準緩和型保険でも通常の保険と同じような保障内容が選べることや、自由にカスタマイズできる商品もあるので、既契約の有無やライフスタイルに合わせて複数商品から比較・検討することをおすすめします。
ニッセンライフでは複数の保険会社の取り扱いがあり、お客さまのご希望に合わせて商品のご紹介・ご説明・申し込みのお手伝いを行っております。
ぜひお気軽にお問合せください。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法
原発性胆汁性胆管炎の治療法
●原発性胆汁性胆管炎の治療法
原発性胆汁性胆管炎に対する根本的な治療法は、まだ確立されていません。
ウルソ®による病気の進展抑制効果が確認されており、第一選択薬となってはいますが、すでに進行してしまった場合には、病気の進行を止めることは困難です。
薬物治療をおこなっても改善がなく、病態が進行した場合には、肝移植が唯一の治療手段となります。
また、自己免疫性疾患や胆汁うっ滞、肝硬変に関連してあらわれる症状、合併症に対する予防や治療も必要となります。
●患者指導
現在では、早期に診断を下せるようになったことや、ウルソ®が病気の進行を遅らせられるようになったことから、患者の7〜8割は肝硬変には至っていないとされています。
無症候性の場合には、症状が現れない限り予後は一般の方と変わらず、日常生活に特別の制限はありません。
一方、すでに症状が出ているsPBC(症候性)の場合には肝機能に応じた生活指導や食事療法が必要となります。
●原発性胆汁性胆管炎と日常生活の注意点
原発性胆汁性胆管炎は慢性的に進んでいく病気です。症状が落ち着いている時期でも、定期的な通院と検査による経過観察がとても重要です。
血液検査では肝機能や胆汁うっ滞の程度、自己免疫に関わる指標などが定期的に確認されます。また、腹部エコーによる肝臓や胆管の状態のチェック、骨密度検査なども必要に応じておこなわれます。
日常生活では、肝臓に負担をかけない工夫が求められます。たとえば、アルコールは原則として控えることが望ましいでしょう。また、体調管理や栄養バランスのとれた食生活、過労にならないように気を付けることや感染症の予防にも注意が必要です。
さらに、原発性胆汁性胆管炎は自己免疫の異常が関わる病気であるため、シェーグレン症候群や関節リウマチ、甲状腺疾患(橋本病)など、他の自己免疫疾患を合併することがあります。目の乾燥、関節のこわばり、全身倦怠感などの症状があれば、早めに主治医に相談するようにしましょう。
この病気と向き合うには、医療者との信頼関係を築き、自分の状態を正しく理解しながら、長期的に治療を継続していくことが大切です。
●原発性胆汁性胆管炎そのものに対する治療
ウルソ®は、原発性胆汁性胆管炎に対して効果が認められた薬です。胆道系酵素の低下作用に加え、肝細胞の改善や肝移植、死亡までの期間が延長されるという効果が確認されています。
ウルソ®での効果が乏しい場合、ビザフィブラート(ベザトール®)の使用が検討されます。原発性胆汁性胆管炎に対しては保険適用外ですが、合併する脂質異常症に対しては使用可能です。
こうした薬物療法をおこなっても肝機能の悪化が進み、黄疸が高度になると効果が乏しいことが予想されます。その場合、最終的には肝移植が必要となります。
無症状の場合に薬物療法をおこなうかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれています。血液検査のALPが正常上限の1.5倍を超えている場合には、すぐに薬物療法を開始、それ以下の場合には3〜4ヶ月に1回肝機能を測定し、胆道系酵素がこのレベルに達した時点で投与をおこなうことがすすめられています。
●原発性胆汁性胆管炎に伴う症状・合併する症状に対する治療
原発性胆汁性胆管炎に伴う症状としては、皮膚のかゆみが最もよくみられます。
このかゆみは黄疸が出現する前からあらわれることもあります。血液中の胆汁酸の増加などが原因と推測されていますが、明らかなメカニズムは不明です。日中よりも夜間に悪化することが多く、肝機能障害が進行するにつれて軽くなることもあります。
かゆみの症状や、骨粗しょう症など合併症がある場合は、それぞれに適応した投薬治療をおこないます。
原発性胆汁性胆管炎の予後を予測する因子としては、血液中の総ビリルビン値が最も重要と考えられています。
総ビリルビン値が2.0mg/dLになると約10年、3.0mg/dLになると約5年、6.0mg/dLになると約2年以下の余命であると予想されます。この場合には、肝移植が考慮されます。
このように、血液検査の結果から病気の進行具合をある程度予測することで、適切なタイミングで治療や肝移植の判断を行うことができます。定期的な検査を受けながら、自分の体の状態を把握しておくことが大切です。
治療費
原発性胆汁性胆管炎の治療費
基本的には外来診療ですが、肝移植をする場合には入院が必要です。
治療費用例 入院日数 ~数週間〜1ヶ月以上~
医療にかかる費用
原発性胆汁性胆管炎の治療は基本的には通院でおこなわれますが、病気が進行して肝不全に至った場合などには、肝移植が検討されることがあります。肝移植には公的医療保険が適用されるため、肝移植にかかる医療費の自己負担額は、3割負担の場合およそ68万円程度になります。
また、肝移植に関連する医療では、抗HLA抗体検査を実施する場合は、さらに数万円の加算が必要となることがあります。さらに、手術そのものに加えて、全身麻酔管理費用や手術加算、ICU(集中治療室)での管理加算などが別途かかる点にも留意が必要です。
入院日数については個人差がありますが、肝移植の場合は数週間から1ヶ月以上の入院が必要になるのが一般的です。なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。病気データ
原発性胆汁性胆管炎のデータ
2018年に厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班(以下、厚労省研究班)が全国疫学調査をおこないました。その結果、全国の原発性胆汁性胆管炎患者数は推定約37,000名、人口10万人当たりの有病率は33.8(人口10万人あたり33.8人という意味)でした。2004年におこなわれた全国疫学調査では有病率11.6(人口10万人あたり11.6人という意味)だったため、14年間でおよそ3倍に増加し、ほぼ欧米並みとなりました。男女比は2004年に約1:7でしたが、2018年には約1:4.3であり、相対的に男性患者が増加していました。発症しやすい年齢は女性50歳代、男性60歳代でした。
出典
厚生労働省難治性疾患政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班
「原発性胆汁性胆管炎(PBC)の診療ガイドライン(2023 年)」
https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/080/image/PBCguideline.pdf
厚生労働省難治性疾患政策研究事業
「患者さん・家族のための「原発性胆汁性胆管炎(PBC)ガイドブック」」
https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/080/image/PBCguidebook.pdf
公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター
「原発性胆汁性胆管炎(指定難病93)」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/93
医療情報の監修

和田 蔵人
プロフィール
佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。
地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。
目次
よくある質問
「原発性胆汁胆管炎と保険」に関する相談例
持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、原発性胆汁胆管炎の方から多くのご相談があります。
主な質問とその回答例をご紹介します。
原発性胆汁胆管炎は難病に指定されていますが、保険に入れますか?
回答はこちら
難病で治療中でも告知項目に該当がなければ引受基準緩和型保険に加入できる可能性があります。
引受基準緩和型保険であれば、万が一原発性胆汁胆管炎が悪化して入院や手術が必要になった場合でも保障されるため安心です。
半年前に一時的に症状が悪化し入院をして治療を受けていましたが引受基準緩和型保険に入れますか?
回答はこちら
1~2年以内に入院や手術で治療を受けたことがある場合は、の予定がある方は加入が難しいです。
引受基準緩和型保険では、「過去1~2年以内に入院をしたこと手術を受けとことがあるか」という告知項目があるため、半年前ということであれば該当するので加入できません。
健康状態の告知が必要ない無選択型保険であれば入れる可能があります。
原発性胆汁胆管炎以外にも治療している病気がありますが保険に入れますか?
回答はこちら
告知項目に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。
複数の持病があっても告知項目に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。
病名や治療状況によって検討しやすい商品が異なるため、複数の商品で比較・検討されることをおすすめします。
相談をする
ニッセンライフでは、原発性胆汁性胆管炎の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。
電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み
対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み


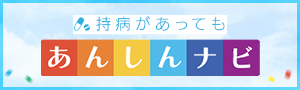
willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。