緑内障でも入れる・加入できる保険

病気解説
緑内障とは
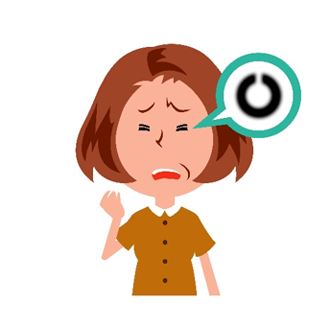
緑内障は、目と脳をつなぐ視神経が傷つくことで徐々に視野が欠けていく病気です。日本では40歳以上の約5%(20人に1人)に緑内障があるとされ、決して珍しい病気ではありません。主な原因は眼圧の上昇だと考えられており、眼球内を循環する液体(房水)の排出がうまくいかなくなることで眼圧が上がり視神経が圧迫され、損傷してしまいます。ただし、眼圧が正常範囲内なのに発症する正常眼圧緑内障も多く存在し、眼圧以外にも視神経の血流低下や遺伝素因など複数の要因が関与すると考えられています。
緑内障の分類
緑内障は大きく原発緑内障と続発緑内障に分類されます。原発緑内障はさらに、房水の出口である隅角(房水の出口)が広い開放隅角緑内障と、隅角が狭い閉塞隅角緑内障に分けられます。
開放隅角緑内障は日本人に最も多いタイプで、ゆっくりと進行します。正常眼圧緑内障もこの開放隅角緑内障に含まれ、眼圧が20mmHg以下でも視神経が傷つくタイプです。
一方、閉塞隅角緑内障は隅角が狭くふさがることで急激に眼圧が上昇し(急性緑内障発作)、放置すると短期間で失明する恐れもあるため緊急治療が必要になります。
続発緑内障には、ぶどう膜炎や糖尿病、ステロイド点眼の副作用など他の要因で眼圧が上がる場合が含まれます。さらに、小児期に発症する先天的な発達緑内障もあります。
緑内障の症状
緑内障の初期には自覚症状がほとんどありません。眼圧が少し高い程度では痛みなどの異常を感じない上、両目で見えている範囲を補い合うため、視野の一部が欠けても患者自身が気づくことは稀です。視野障害はまず周辺部から進行し、病気がかなり進行して視野の中心近くが侵されるまで日常生活で支障を感じにくいという特徴があります。一方、閉塞隅角緑内障では発作時に眼圧が40〜60mmHgまで急上昇するため、視界のぼやけや虹が見えるといった症状のほか、激しい目の痛みや頭痛、吐き気を伴います。発作前は無症状でも、このような症状が出た場合は緊急で眼科を受診する必要があります。
緑内障の検査
緑内障の検査は、病気の早期発見と進行状況の把握に不可欠です。まず、眼圧検査では、目の硬さ(眼圧)を調べます。眼圧は、ゴールドマン圧平眼圧計などの接触式や、空気眼圧計といった非接触式の機器を用いて測定します。ただし、眼圧が正常範囲内であっても視神経にダメージが及んでいる正常眼圧緑内障も存在するため、眼圧検査だけでは十分な診断が難しいことがあります。
次に、隅角検査がおこなわれます。この検査では、ゴニオレンズという特殊なレンズを使用し、点眼麻酔後に眼球の隅角(房水が排出される出口部分)の状態を細隙灯顕微鏡で観察します。隅角の広さや異常の有無を確認することで、緑内障の病型や治療方針の決定に重要な情報が得られます。
また、眼底検査では、瞳孔を拡大させた状態で眼の奥、特に視神経乳頭の状態を観察します。視神経乳頭の形状やくぼみの程度、網膜の状態などを詳細にチェックすることで、視神経へのダメージや緑内障の進行度が評価されます。眼底検査には、直接観察する方法や眼底カメラを使用して記録する方法があります。
さらに、OCT検査(光干渉断層計検査)では、網膜神経線維層の厚みや視神経乳頭の見た目に変わりがないかを測定します。体に負担をかけず短時間で済むため、初期段階の緑内障の診断や進行の有無の確認などに有用です。
最後に、視野検査では患者が実際にどの範囲を見ることができるか、またはどの部分で感度が低下しているかを調べます。自動視野計などの機器を用いて、光刺激に対する反応を記録し、視野欠損の程度や進行具合を把握します。緑内障は初期には自覚症状がほとんどないため、こうした視野検査による定期的な検査が重要です。
このように、眼圧検査、隅角検査、眼底検査、OCT検査、そして視野検査といった複数の検査を組み合わせることで緑内障の診断が下され、治療方針が決定されます。
保険加入
緑内障でも入りやすい保険とは
緑内障で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に入れる可能性があります。
また治療状況や条件を付けることで通常の保険でも検討できる可能性もあります。
緑内障で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをご紹介します。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
緑内障で治療中・治療歴があっても通常の保険に入れる可能性があります
緑内障と診断されたばかりや、これから検査・入院・手術の予定がある場合、引受基準緩和型保険や無選択型保険であっても入ることはできません。
治療方針が定まった段階で保険を検討するようにしましょう。
緑内障で治療中の方が通常の医療保険を検討する場合、手術の有無や視力や視野に異常があるかどうかがポイントになります。
- 治療歴・期間(診断されてから何年経過しているか)
- 手術の有無
- 視力や視野の異常があるか
- 緑内障以外で治療している病気の有無
※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。
健康状態だけではなく、職業などその他の告知や申込内容で総合的に審査判断されます。
緑内障は通常の保険に加入できる場合でも、特定の部位や病気に関しては保障(補償)をしないといった条件が付く可能性が高いです。
例えば、目を保障(補償)しないという条件が付いた場合、緑内障を含め白内障など目に関する病気全般が保障(補償)の対象外になります。
保障(補償)されない期間は、5年などの一定期間の場合もあれば全期間の場合もあります。
どのような条件で引き受けできるのかは保険会社によって基準が異なるため、ご自身の健康状態にあわせて保険会社や商品を選ぶのがおすすめです。
ただし、病気の引受基準などは開示されておらず個々で調べるのは大変なので、複数の保険会社を取り扱っているニッセンライフにぜひご相談ください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

持病の悪化にも備えたいなら「引受基準緩和型保険」がおすすめ
引受基準緩和型保険は、通常型保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。
持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。
ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があるため、まずは通常型で加入できないか検討してから引受基準緩和型保険を検討するようにしましょう。
引受基準緩和型保険も加入が難しいという場合は、無選択型保険があります。
医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。
ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始時前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。
ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。
保険選びと一言でいっても病状や生活スタイル、すでに加入している保険があるかどうかなどによって、必要な保障や商品は異なります。
保険選びでお困りの場合は、ぜひニッセンライフまでご相談ください。
お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。
ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。
とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法
緑内障の治療法
緑内障の治療には大きく分けて薬物療法(点眼薬による治療)、レーザー治療、手術治療の3種類があります。いずれも眼圧を下げて視神経への負担を減らし、病気の進行を抑えることを目的とします。現在、眼圧下降以外に進行を抑えられる確実な方法はなく、正常眼圧緑内障でも発症前の眼圧より十分下げることで進行を遅らせられることが証明されています。以下では各治療法の概要と適応や副作用、効果について説明します。
●薬物療法(点眼治療)
緑内障ではまず点眼薬による眼圧下降治療がおこなわれます。現在、眼圧を下げる点眼薬には以下のような種類があります。
- プロスタグランジン関連薬
眼圧を下げる効果が高く第一選択となることが多い点眼です。眼房水(目の中の一部の空間にある水分)の流出を促進する作用があり、副作用として眼の充血やまつ毛が濃く長くなる、虹彩色素沈着などがあります。 - β遮断薬
房水の産生を抑えて眼圧を下げます。全身に吸収されると心拍数低下や気管支収縮など全身に副作用が出ることがあるため、喘息や心臓疾患のある方は注意が必要です。 - 炭酸脱水酵素阻害薬
房水産生を抑制する点眼薬です。一部は内服薬(アセタゾラミドなど)もあり即効性がありますが、内服では手足のしびれや倦怠感など副作用が出やすいため長期使用は慎重におこなわれます。点眼の場合、目が充血したり口の中に苦味を感じたりすることがあります。 - α2作動薬
房水産生の抑制と流出促進の両方の作用を持つ点眼薬です。比較的副作用は少ないですが、長期使用でアレルギー性結膜炎を起こすことがあります。 - Rhoキナーゼ阻害薬
比較的新しい作用機序の点眼薬で、房水の流出路である線維柱帯からの排出を促進して眼圧を下げます。副作用として充血が出やすいですが、他の点眼と効き方が異なるため併用されることがあります。
これらの点眼薬を患者ごとに効果や副作用を見ながら1種類の薬剤から開始し、十分に眼圧が下がらなかったり、視野の進行が早かったりする場合は、複数の点眼薬を併用します。点眼薬の中には全身に影響する副作用を持つものもあり、また長期使用によりまぶたの炎症や結膜炎を起こす可能性もあります。医師の指示を守り、異常を感じたらすぐに相談することが重要です。点眼治療で眼圧が目標まで下がらない場合や、下がっていても視野障害の進行が認められる場合には次の段階の治療が検討されます。
●レーザー治療
レーザーを用いて眼圧を下げる治療もおこなわれます。開放隅角緑内障に対しては、隅角の線維柱帯(房水の流出路)にレーザーを当てて房水の排出を促す選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)が一般的です。SLTは低エネルギーのレーザーで組織へのダメージが少なく、必要に応じて繰り返し治療可能であるという利点があります。点眼薬による治療の負担や副作用を減らし、手術を先送りできるメリットも期待できます。一方、閉塞隅角緑内障では急性発作の予防や治療のために、レーザーで虹彩に小孔を開け房水の通路を確保するレーザー虹彩切開術がおこなわれます。さらに重症例では、毛様体にレーザーを当てて房水産生自体を抑える毛様体光凝固術をおこなうこともあります。レーザー治療は切開を伴わず外来で短時間でおこなえる利点がありますが、一時的に眼圧上昇や炎症を起こすリスクもあり、安全性は高いものの合併症が全くないわけではありません。適応や効果について主治医とよく相談して決定することが大切です。
●手術治療
点眼薬やレーザーでも十分な眼圧下降が得られない場合、手術による治療が検討されます。手術では物理的に房水の排出路を確保し、眼圧を大幅に下げることが可能です。代表的な手術には、線維柱帯切除術と線維柱帯切開術があります。
●線維柱帯切除術(濾過手術)
目の白目部分にフィルターのような穴を作り、新たな房水の排出口(濾過胞)を形成する手術です。トラベクレクトミーとも呼ばれ、最も一般的におこなわれる緑内障手術です。眼圧下降効果は大きいですが、手術部位から感染を起こすリスクや、眼圧が下がりすぎることによる低眼圧症、白内障の進行などの合併症がありえるため、手術後も定期的な経過観察が必要です。
●線維柱帯切開術(流出路再建術)
隅角から線維柱帯そのものを切開して房水の排出をスムーズにする手術です。先天緑内障などでおこなわれる方法ですが、成人の難治例にも適応されることがあります。近年では小さなデバイスを用いる低侵襲手術も登場しています。例えば線維柱帯や隅角にチューブやスタントを留置する流出路再建デバイス(iStent®やMicroShuntなど)の挿入術や、眼内にバルブ付きチューブを挿入して房水を眼外へ誘導するチューブシャント手術(アーメドバルブなど)もおこなわれています。
これら手術は薬物やレーザーに比べ眼圧を大きく下げられる反面、手術による体への負担や合併症のリスクもあります。そのため通常は薬物治療から開始し、必要に応じて段階的にレーザー、手術へ移行するのが一般的です。主治医とリスクとベネフィットを十分相談した上で、自分の病状に合った治療法を選択することが重要です。
治療費
緑内障の治療費
日本では緑内障の診療は多くが健康保険の適用内でおこなわれ、患者は医療費の一部(一般的に3割)を負担します。費用は治療内容や入院日数によって大きく異なりますが、ここでは入院して手術を受けた場合の一例を示します。高額な医療費がかかった場合には高額療養費制度による負担軽減も受けられます。
治療費用例 〜入院日数 15日〜
2024年に某病院にて緑内障を治療した80歳男性の治療費実例にもとづき、患者が負担しなくてはならない費用を概算しました。この患者は15日間入院し手術を受け、健康保険適用の医療費総額が90万円でした。この場合の費用内訳は以下のようになります。
| 医療にかかる費用 | |
|---|---|
| ①健康保険適用医療費総額 (保険診療分) | 900,000円*1 |
| ②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分) | 0円*1 |
| ③医療費総額(①+②) | 900,000円 |
| ④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%) | 270,000円 |
| ⑤高額療養費の自己負担限度額*3 | 86,430円 |
| ⑥高額療養費による割戻額(④-⑤) | 183,570円 |
| ⑦医療費自己負担額(②+⑤) | 86,430円 |
| その他の自己負担費用の概算 | |
| ⑧入院時食事療養費標準負担額*4 (1食490円×入院日数×3回) | 22,050円 |
| ⑨差額ベッド代 (1日6,714円×入院日数)*5 | 100,710円 |
| ⑩雑費(1日1,500円×入院日数)*6 | 22,500円 |
| ⑪合計自己負担額(⑦+⑧+⑨+⑩) | 231,690円 |
*1 ①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。
*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)
*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。
*4 (1)の保険診療の食事療養に係る費用のうち、厚生労働大臣が定める一般の方の1食あたりの標準負担額490円(令和6年6月以降)に対して、1日を3食として入院日数を乗じた金額。
*5 (2)の選定療養のうち、いわゆる差額ベッド代に係る費用。「主な選定療養に係る報告状況」厚生労働省 令和5年7月1日現在より1日あたり平均徴収額(推計)の合計値6,714円に入院日数を乗じた金額。
*6 付添いの家族の食事代や交通費、日用雑貨の購入費等の費用を1日あたり1,500円と仮定し、入院日数を乗じた金額。
なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。
病気データ
緑内障のデータ
有病率と発症リスク(年齢・性別)
緑内障は加齢とともに有病率(罹患率)が上昇します。岐阜県多治見市でおこなわれた大規模疫学調査(多治見スタディ)によれば、40歳代の緑内障有病率は約2.2%(男性2.1%、女性2.3%)でしたが、50歳代で2.9%、60歳代で6.3%、70歳代では10.5%に達しました。80歳以上では全体で11.4%と報告され、特に80代男性では16.4%と非常に高い有病率でした。このように高齢になるほど緑内障になる人の割合は増え、70代では実に10人に1人が緑内障という計算になります。また性別では一般的に閉塞隅角緑内障は女性に多いとされますが、多治見スタディでは80代以上の男性で有病率が高く、地域や集団によって多少の差異があります。いずれにせよ年齢が最大のリスク要因であり、40歳を過ぎたら定期的に目の検診を受けることをおすすめします。実際、多治見スタディでも緑内障患者の約90%がこの調査で実施された眼科検診で初めて発見されたケースであり、自覚症状がなくても検診で早期発見することが重要であると示されています。若年者の発症は多くありませんが、20〜30代でも強度近視や家族歴(血縁者に緑内障患者がいる場合)、長期にわたりステロイドを使用していることなどがあると発症リスクが高まります。
失明リスクと早期発見・治療の重要性
緑内障は日本における中途失明(後天的に失明すること)の原因第1位です。視神経が一度損傷すると現在の医療では回復が難しく、進行して視野が狭くなり視力低下が起これば、最悪の場合失明に至ります。ただし緑内障の進行は多くの場合ゆっくりで、適切な治療によりかなりの期間視力・視野を維持できることも事実です。実際には緑内障と診断されても、適切な治療と経過観察を続ければ失明を回避できる可能性が高いとされています。重要なのは早期発見・早期治療であり、症状が出る前に治療を開始できれば視野障害の進行をある程度コントロールできます。逆に発見が遅れて末期まで進行した状態では、治療をおこなっても満足のいく効果が得られにくくなります。そのため、日本緑内障学会などでは一般市民への啓発活動を通じて受診率向上に努めています。自覚症状がなくても定期的に眼科検査を受けることで緑内障の早期発見につながり、適切な治療によって失明を防ぐことができるのです。
出典
公益財団法人日本眼科学会「緑内障」
https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=35
公益財団法人日本眼科医会「よくわかる緑内障―診断と治療―」
https://www.gankaikai.or.jp/health/49/index.html
日本緑内障学会「「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)」報告」
https://www.ryokunaisho.jp/general/ekigaku/tajimi.php
公益財団法人長寿科学振興財団:健康長寿ネット「緑内障」
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ryokunaishou/about.html
医療情報の監修
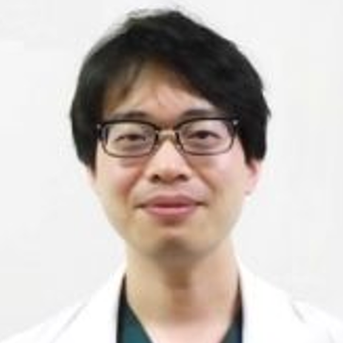
栗原 大智
プロフィール
2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。
「視界の質=Quality of vision(QOV)」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。
目次
よくある質問
「緑内障と保険」に関する相談例
持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、緑内障の方から多くのご相談があります。
主な質問とその回答例をご紹介します。
緑内障と診断されましたが、治療はなく経過観察のみです。保険に入れますか?
回答はこちら
通常の保険でも引受基準緩和型保険でも入れる可能性があります。
ただし、通常の保険の場合、目に関して保障しないという条件が付く可能性があります。
緑内障が悪化して入院や手術が必要になったときにも備えたい場合は、引受基準緩和型保険の検討をおすすめします。
緑内障の治療のため手術の予定がありますが、保険に入れますか?
回答はこちら
入院や手術の予定がある場合は、いかなる保険も入ることはできません。
手術が終わり、その後の治療状況などによっては、通常の保険に入れる可能性はあります。
なお、引受基準緩和型保険の場合1~2年以内に入院をしていると告知に該当して申し込みできないため、延期になります。
緑内障以外の病気で治療中ですが保険に入れますか?
回答はこちら
病名や治療歴によっては保険に入れる可能性があります。
お問合せいただければ状況をおうかがいの上最適な商品をご紹介することができるので、ぜひお電話・ご相談ください。
相談をする
ニッセンライフでは、緑内障の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。
電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み
対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。
電話番号
{{nlifeTel.num}}
受付時間
- 平日:
- 9:00~19:00
※土・日・祝日休み


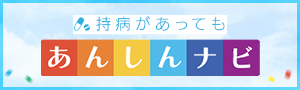
willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。