公的医療とは「出産育児一時金・家族出産育児一時金」
出産時に国からもらえるお金(出産育児一時金・出産手当金)

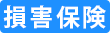
一般的な妊娠や出産の場合、病気ではないため健康保険が適用されず、とくに入院費や分娩費が高額になる傾向があります。これを補うのが出産育児一時金や、出産育児手当金です。
出産育児一時金

公的医療保険の加入者(被保険者)が出産をした時は「出産育児一時金」、被扶養者である家族(サラリーマンの妻など)が出産をした場合は「家族出産育児一時金」が支給されます。支給額は両方とも同金額で、50万円*1です。ただし産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合は48万8,000円です。なお、双子を出産すると2人分が給付されます。
●被保険者期間が継続して1年以上ある場合、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産した場合も出産育児一時金が支給されます。
●被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産した場合、労災保険で補償を受けていても、出産育児一時金も支給されます。
出産一時金の受け取り方
出産育児一時金の受け取り方法には、下記の3種類があります。
| 直接支払制度 | 妊婦に代わり、医療機関が出産一時金の請求と受け取りを行う制度。 |
|---|---|
| 受取代理制度 | 直接支払制度を導入していない産院や病院で採用されています。出産 |
| 産後に申請する (直接請求) | 退院時には、出産費用を全額支払い、その後、健康保険に申請手続き |
出産手当金
健康保険の被保険者本人が、出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき、産前42日(多胎分娩98日)から産後56日までの期間、欠勤一日につき標準報酬日額の6割が支給されます。出産予定日が遅れた場合は、遅れた日数分給付日が増えます。
出産手当金は、勤めている人が加入している公的医療保険の制度ですので、被保険者本人のみが適用となる制度です。そのため扶養家族の人には給付されません。また自営業やアルバイトの人など国民健康保険加入者には、この制度はありません。
出産手当金が受けられる期間と手続き
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。ただし、期間中に出産手当金の額より多い報酬が支給された場合は、出産手当金は支給されません。
出産手当金の支給される金額
標準報酬日額の3分の2に相当する金額を受け取れます。具体的な数式は次の通りです。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 *2 】÷30日 ×(2/3)
*2 支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・30万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
上記を比べて低いほうの額を使用して計算します。
※記載内容は2023年6月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。
免責・禁止事項
このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2023年6月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。
有限会社エヌワンエージェンシー
森田直子


willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。